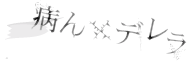 |
|
| ■ 小学生編 第一話「出会い」 | |
| TOPに戻る 次のページ> | |
悠里と出会った翌日。 恭司は授業が終わるとすぐに教室を飛び出し、自宅にもよらず、まっすぐ富士山公園に向かった。 帰り際、山岸に声を掛けられたが、そばに原田の姿が見えたこともあって、誘いは丁重に断った。 山岸の影に隠れながら原田とサッカーをするよりは、昨日出会った幽霊のような少女ともう一度話がしたかったし、そのほうがはるかに楽しい放課後になるような気がしたからだ。 下校時間が始まってから間もないこともあってか、園内に子供たちの姿はまだあまり見られず、昨日は満員に近かった遊具群付近も閑散としていた。悠里と過ごした件のブランコにも、まだ誰も乗っていなかった。 昨日と同じように砂を払い、ブランコに座ると、恭司は空いている隣のブランコに自分のランドセルをおろした。こうしていれば、悠里が来るまでに他の子供がここに座る事はない。 秋の空の日は、まだ中途半端な高さにあった。悠里が昨日と同じくらいの時間帯に現れるなら、大分時間がある。恭司はランドセルを開き、中から筆箱と算数のドリルを取り出した。 彼女が今日もここに来るかどうかはわからなかったが、もし来たとして、宿題の事で頭を一杯にしたままなのはどうにも気持ちが悪い。昨日のように探り探りでなく、もっとちゃんとした会話をして、彼女の話をきちんと聞きたい。恭司はそう思っていた。 ひざの上で算数のドリルを開き、学校で指定された問題を解きながら、恭司は悠里を待った。日が沈みはじめ、周囲が次第に暮れ色に染まりだした頃、夕日に照らされて伸びる恭司の影に、別の小さな影がゆっくりと近づいてきた。 顔を上げ、隣のブランコに目を向ける。そこには、長い黒髪と全身に纏った陰鬱な雰囲気が特徴的な一人の女の子が佇んでいた。昨日見たのと同じようなデザインのワンピース着て、ぼろぼろのランドセルを背負っている。 女の子は、恭司のランドセルをガラス玉のように虚ろな瞳で見つめたまま動かない。 恭司は、慌てて自分のランドセルを隣のブランコからどけた。 「来てくれたんだ。よかった」 自分の声が少し震えていることに、恭司は気がついた。 昨日話をしたのだから、少しは恐怖心も薄れているかと思ったのだが、身体の方は彼女の放つ異様な雰囲気にまだ慣れていないようだった。 「今日は早かったんだね。昨日くらいの時間にくると思ってた」 「今日は、もっといっぱいお話したかったから。ありがとう。今日も来てくれて」 昨日と変わらない、不明瞭な声で悠里は言った。 「僕ももっといろいろ話したかったから。昨日中途半端なところで川添さん帰っちゃったからさ。ちょっと気になって」 「気になるって、私の事?」 「うん。何で声掛けてきたのかなとか、昨日聞けなかった事、色々」 「……そう」 ゆったりとした動きで、悠里はブランコに座った。 それを見て、恭司はすこしずつ、自分のブランコを動かし始める。 「えっと、そうだ。昨日の飴、おいしかったよ。ありがとう」 「どういたしまして」 恭司の速度に合わせるように、悠里も自分のブランコをこぎだす。 「あの、昨日なんで突然声かけてきたの? 僕の事しらなかったんだよね?」 「……うん」 「なんとなくとか言ってたけど、それだけじゃないよね? もしかして川添さんって……」 そこまで言って、恭司は口を噤んだ。 いくらなんでも、友達いないの? なんて聞きづらい。なにか別の言い方をしないと。 「私、友達いないから。誰か一緒に遊んでくれないかって、そう思ってたまに人に声掛けてるの。だけど、恭司君みたいに私としゃべってくれる人、全然いないの」 恭司の心情を察したかのように、悠里は自分から話し始めた。 自分をいきなり名前で呼んできたことに恭司は驚いたが、不思議と嫌な感じはしなかった。むしろ名前で呼ばれたことで、彼女の纏う陰鬱さが、少しだけ薄らいだように感じられた。 地面を軽やかに蹴り上げながら、悠里はどこか嬉しそうに続ける。 「恭司君、いい人だよね。怖がらないでちゃんと私とお話してくれた。ちゃんと私と遊んでくれた。すごく嬉しかった。他の人は、私の事見ると逃げちゃうから」 「そう……」 それはそうだよ。僕だって最初は幽霊みたいだって思ったもの、なんて事は、口が裂けても言えなかった。第一、あんな風に泣かれたら、僕みたいなやつが逃げられるわけないし、もっと気の弱い子供なら逆に泣き出してしまってもおかしくない。自分に友達ができない理由を、この子はちゃんとわかっているんだろうか。 「もっと、恭司君の事知りたいな。もっとたくさん、知りたいな」 悠里の声音が弾んでいくのと並行するように、ブランコを漕ぐ速度も、徐々にあがっていく。 「恭司君のお家ってどこにあるの? 恭司君の好きな食べ物ってなに? 恭司君、動物とか好き? 恭司君はどんな勉強が得意なの?」 今までとは違うまくし立てるような口調で、悠里は矢継ぎ早に質問してくる。どの質問にも具体的な関連性はなく、ただ思いついたことを次々と口にしている、そんな感じだった。 「川添さん、質問なら一個ずつにしてよ」 「恭司君、恭司君、恭司君、恭司君……」 悠里は憑かれたように、恭司の名前を繰り返し呼んでいる。さすがに恭司も、ここまでくると少し異常なものを悠里から感じ始めていた。 恭司は声を張りあげ、悠里に呼びかけた。 「川添さんってば!」 呪詛のようにもなりかけていた悠里の言葉は、それでぴたりとやんだ。鉄鎖が耳障りな音を立てながらきしみ、ブランコの動きが緩やかに落ち着いていく。 「ごめんなさい。私……」 悠里はうなだれながら、心底悲しそうな、申し訳なさそうな声で言った。 「こんなだから、だめなんだね、私。ママの言うとおり、汚い人間なんだね。ごめんなさい」 悠里の突然の豹変振りと、あまりにも沈痛な声に、恭司は困惑した。 いったいどうしたんだろう。急に喜びだして、急に沈み込んでしまった……。 「私、嬉しくって……ひさしぶりだったから。こんなに同い年の子としゃべったの。うまくできなくて、ごめんなさい」 そこでようやく、恭司は納得した。 彼女は、同級生と話せるのが純粋に嬉しかっただけだ。今まで邪険にされてきた分、うまく言葉を継げなかっただけで、あの質問の嵐も、ただもっと恭司のことが知りたかっただけのことだった。 言うなればただの自己紹介のようなものだ。それだけのことだったのに、少し臆してしまった。僕は、馬鹿だ。 「本当にごめんなさい。もう帰るね。そろそろ時間だし。さようなら」 悠里はブランコを止めて立ち上がると、悄然と頭を垂れたまま、公園の出口に向かおうとし始めた。 長い前髪が余計に垂れ下がり、完全に表情は見えなくなっている。だが、少なくともひどく悲しんでいる事だけは、恭司にも理解できた。 「待って。川添さん」 ランドセルに荷物をつめながら、恭司は慌てて悠里の後を追った。 「これ。これ、受け取って欲しいんだ」 恭司はポケットの中から、小さな飴玉をひとつ取り出し、悠里に差し出した。 昨日、もし明日悠里に会えたら、とお礼のために自宅から持ってきたものだった。悠里からもらったものとは味も見た目も違う、黄色い包装紙に包まれた小さな飴玉だ。 恭司の手のひらに乗った飴玉を見て、密集した髪の間から見える悠里の真っ黒な眼が、大きく見開かれる。 「これ……」 「うん。昨日のお礼。それと、さっきのお詫び」 「で、でも、もらえないよ。私が悪いんだし」 ためらうように、悠里はかぶりを振った。 「いいんだ。僕も、嬉しかったから。今日も川添さんに会えて。また明日も会えるかな?」 「会えるかもしれないけど、でも」 「もっと、ゆっくりやっていこうよ。ゆっくり仲良くなろう。ね?」 「うっ……」 悠里の全身が、小刻みに震え始めた。 まさか昨日のように泣き始めたのではないかと一瞬恭司はひるんだが、俯いていた顔を上げた悠里の目を見て、その心配が杞憂に終わった事を悟った。 昨日と同じように、悠里の大きな目は、綺麗な湾曲を形作っていたのだ。 「うん。また、明日ね」 差し出された恭司の手から、悠里はしっかりと飴玉を受け取った。 小さく手を振り、何度も恭司の方を振り返りながら、ゆっくり公園の出口へ向かっていく。 恭司も大きく手を振り返しながら、いつまでも悠里の後姿を見送っていた。 自分の胸のうちを、温かいものが染み入っていくような、不思議な感覚がした。 9月14日(金)晴れ 今日も公園できょうじ君に会った。 きょうじ君はやっぱり優しい男の子だ。私がいけないことしたのにあめ玉をくれた。 はやく明日にならないかな。はやく会いたいな。いっぱいお話したいな。 今日はちゃんとママの言いつけを守ったのに、いっぱいぶたれてしまった。 ぶさいくな顔をみせるなって、きもちわるいって言われた。いつものことだ。 たくさん叩かれたけど、きょうじ君からもらったあめをにぎっていたらそんなことどうでもよくなってしまった。 きょうじ君のあめ玉はまほうのあめ玉だ。あまくておいしくて、大好き。 明日は私もあめ玉を持っていこう。きょうじ君もよろこんでくれるといいな。 おしまい |
|
| TOPに戻る 次のページ> | |